地方移住にちょっと興味がある。
今の働き方も、なんだかこのままでいい気がしない。
でも、いきなりは無理。
そんなふうに感じたことはありませんか?
コロナ禍以降、
リモートワークや働き方の自由度が高まったとはいえ、
「暮らしをまるごと変える決断」
にはまだ遠いという方は多いと思います。
私自身もそうでした。
この記事では、
「まずは短期の暮らし体験から始めてみた」
私のリアルな移住検討プロセスをもとに、
実際に試してよかったこと・想定外だったこと・
働き方のヒントになった気づきまでをまとめています。
“ちょっと変えたい”を行動に変えたいあなたの、
ヒントになれば嬉しいです。
コンテンツ
🟪 「働き方を変えたい」と思ったときに都会では得られなかった感覚とは?
「働き方を変えたい」と思い始めたとき、
私の中に最初にあったのは“目に見える不満”ではなく、
“うまく言葉にできない違和感”でした。
会社員としての働き方に大きな不満はなかったし、
仕事もそれなりに評価されていた。
でも、週末にどれだけ自然に触れても、
朝の通勤で満員電車に揺られるたびに、
「なんだか、自分がどこに向かっているのかわからない」——
そんな気持ちになる瞬間が増えていきました。
都市生活の中で感じた
“ずっと何かに追われている”感覚。
便利なはずなのに、なぜか息が詰まる。
買い物も、外食も、娯楽も、
全部あるのに、なぜか満たされない。
それは、私にとって
「働き方を見直すこと=暮らし方を見直すこと」
だったのかもしれません。
自然と隣り合わせの暮らしには、
都市にはない“余白”がありました。
空の広さ、朝の静けさ、季節の移ろい。
それらを日常の中で感じることが、
自分にとってどれほど大切だったか。
それまでの環境では気づくことができなかったのです。
“変えたいのは仕事だけじゃなかった”。
そう気づいたとき、働き方の本質的な見直しが、
ようやく始まったように思います。
🟪 地方移住を検討中の人へ。短期滞在で見えた“暮らしと働き方”のヒント
「じゃあ、実際にどうやって地方移住を考え始めたの?」
と聞かれることがあります。
私にとっての最初の一歩は、
「いきなり移住」ではなく、
“短期でその土地に暮らしてみること”でした。
当時は、ちょうどコロナ禍で出社義務がなくなり、
どこで仕事をしても構わない状況だったんです。
「働く場所が変われば、感覚も変わるかもしれない」——
そんな思いつきに近い動機で、
北海道の新得町と根室市にそれぞれ約2週間ずつ滞在
してみることにしました。
「観光」じゃなく「暮らす」に近い体験
私が意識していたのは、“旅”ではなく“暮らし”としての体験。
地元の小さな宿に泊まり、朝は散歩、
日中はその日に時間を決めて仕事、
それ以外はその土地ならではの
自然や土地の人に触れる時間にしてみました。
地元のお店でお惣菜を買って夕食にしたり、
移住者が営むカフェで会話を楽しんだり。
観光地では出会えない、
その町の日常にできるだけ近づいてみる——
そんな過ごし方を意識していました。
そうやって過ごす中で気づいたのは、
「自然の中にいること」そのものが、
自分の感じ方や思考の質を変えてくれるということ。
朝の空気や、窓から見える緑の風景、
五感で感じる季節の移ろいは、
都会のオフィスでは得られなかったものでした。
「暮らし方」は働き方にフィードバックされる
たとえば、
「今日はどこで仕事しよう?」と考えたとき、
選択肢に“森の中のベンチ”が加わる。
お昼休みに川沿いを歩いてリフレッシュするだけで、
午後の集中力が変わる。
暮らしの質を変えることが、働き方にも直結するんだ
と実感したのは、このときが初めてだったと思います。
検討中の人にこそおすすめしたい「ライトな滞在」
もし今、地方移住に興味があっても
「いきなりは無理」と思っているなら、
まずは1泊でも2泊でもいいので、
“暮らしに触れる旅”をしてみることをおすすめします。
- 宿泊は、地元の人が経営しているゲストハウスがベスト
- 観光地ではなく、地元の人が営むカフェや雑貨店に立ち寄ってみる
- 役場の移住相談窓口に「ちょっと町を見に来たんですけど」と声をかけてみる
ほんの数日の滞在でも、
思った以上にその土地の空気感や、
人の距離感、暮らしやすさが見えてきます。
「地方移住 検討中」という段階のあなたにとって、
“試してみた体験”こそが、
自分に合う暮らし方や働き方のヒントや気づきにつながる——
そんな最初の「確かな手応え」になるかもしれません。
🟪 移住じゃなくても大丈夫。「小さく試す」ことで見えてくるもの
「地方移住には興味がある。
でも、仕事も家庭もある中で、いきなりは無理」
そう感じるのは当然のことです。
私自身も、いきなり移住したわけではありません。
実は、“働き方を変えたいけど移住できない”
という状況の中でも、
できることはたくさんあります。
むしろ大事なのは、
「いきなり大きく変える」よりも、
「小さく試してみる」ことでした。
「ライフスタイルを変えたい」と思ったら、“暮らしのスキマ”を使ってみる
たとえば、平日に2日だけ休みを取って、
地方で“暮らしに近い体験”をしてみる。
宿泊は、観光ホテルではなく
地元の人が営むゲストハウスにする。
地元のカフェに入り、
オーナーやお客さんと何気ない会話を交わしてみる——
そんなシンプルな行動だけでも、
現地に足を運んでみないと見えてこない、
たとえば「朝の空気感」や「人との距離感」みたいな、
本当に大事なことやリアルな情報を得られます。
また、
「あ、自分はこういう空気が好きなんだな」
といった「小さな発見」が、
次の選択肢を考えるヒントになることもあります。
「小さく試す」ことで、“必要な変化”だけが見えてくる
実際に短期滞在をしたとき、
私が得たのは「全部を変える必要はない」
という実感でした。
都会的な便利さが恋しくなることもあれば、
「静かな朝がこれほど心地いいとは…」
という発見もある。
体験してみてはじめて、
「思っていたより重要じゃなかったこと」
「逆に手放せないもの」
がわかるんです。
移住だけが答えじゃない。自分にとっての“快適な距離感”を探すこと
暮らしと働き方は、セットで考える時代
になってきています。
だからこそ、
「暮らしを変える=移住」と思い込む必要はありません。
・都市部に住みながら、月に1度だけ自然の多い場所に通ってみる
・ワーケーションで“場所を変える働き方”を少しずつ取り入れてみる
・週末に都会の喧騒を離れて、“自分を取り戻す時間”を持つ
どれも立派な“ライフスタイルの再設計”です。
「いつか移住できたらいいな」ではなく、
「いまの自分にできる“最初の小さな変化”は何だろう?」
と問い直してみること。
その問いが、
今のあなたにとってのいちばんリアルなスタート地点
になるかもしれません。
🟪働き方を変えたい人が、リモート滞在中にやっておくべきこと
「小さく試してみることで、自分にとって大事なことが見えてくる」
—— それは実感として本当にそうだと思います。
私の場合、その“お試し滞在”を
リモートワークと両立しながら行いました。
だからこそ感じた、
「やっておいてよかったこと」
「これが鍵だった」
というポイントがあります。
これから地方での短期滞在を検討している方に向けて、
働き方を変えたい人が“暮らしに近い体験”をする際に、
意識したいポイントをまとめてみました。
仕事と暮らしを両立するために「環境の下調べ」は必須
まず、滞在先でリモートワークをするなら、
通信環境は絶対に外せないポイントです。
私は滞在先を決める前に、
Wi-Fi環境や電波状況を念入りに確認しました。
それでも、
根室で泊まった宿は中心部から少し外れていたせいか、
携帯の電波が不安定で、
オンライン会議中に何度か音声が途切れる
ということもありました。
テザリングできる端末を持参したり、
ポータブルWi-Fiを準備しておくと安心です。
また、どうしても外せない会議や作業の前日は、
実際にネット速度を測ってみることもおすすめです。
「この時間帯は働く」と決めておくと、現地の体験が濃くなる
せっかく地方に来たからといって、
仕事をずるずる引きずっていては意味がありません。
私は毎朝、
その日一日で集中して仕事に使う時間帯を決めていました。
オンライン会議や締切の迫っている仕事は
優先的に時間を割り当てます。
それ以外の時間帯以外は、
できる限りその土地でやりたいことを優先して実行します。
近くの川沿いを散歩したり、
移住者が営むカフェに立ち寄ってみたり。
食事はできるだけ地元のごはん屋さんに行って、
地元の人と触れる時間を楽しむ。
限られた時間だからこそ、
「この土地での体験をちゃんと味わおう」
という感覚が自然と生まれて、
結果的にその時間が、
仕事への集中力にも良い影響を与えてくれました。
働き方のクセや「自分のリズム」を知るチャンスでもある
意外だったのは、
地方に滞在しているときの方が、
自分の「働きやすいリズム」が見えてきたこと。
たとえば、
午前中は静かな場所で深い思考ができることや、
午後はアウトプット系の仕事の方がはかどる
という自分の傾向。
また、自然の多い場所で過ごすことで、
頭が整理されやすくなる感覚。
これは日常の環境ではなかなか気づきにくいことですが、
場所や時間を意識的に変えることで、
自分の“仕事の調子”を整えるヒントが見えてきた気がします。
地方での短期滞在は、
単に「どこか違う場所で働く」というだけではなく、
“暮らし方と働き方を見直す実験の場”になるのだと、
私は実感しました。
まずは「仕事と暮らしをどう両立するか」
にちょっとだけ意識を向けてみること。
その積み重ねが、
“今の働き方のどこをどう変えたいのか”
を見つける大きなヒントになるかもしれません。
🟪地方移住前の不安をどう解消したか。実体験から話せること
リモート滞在を通じて
「この土地、いいかも」と思えても、
いざ“住む”ことをリアルに想像し始めると、
もうひとつの不安が出てきます。
それが、人間関係や地域に馴染めるかという不安です。
私自身、最初に移住を考えたとき、
実はここが一番大きな心のブレーキになっていました。
「よそ者扱いされたらどうしよう」——移住前にあったリアルな不安
移住というと、
「新しい土地でゼロからのスタート」
と聞こえはいいですが、
実際には“誰も知り合いがいない”
ことの孤独や不安があります。
特に私のように、
地方のコミュニティに馴染みがない者にとっては、
「ご近所付き合いが濃すぎるのでは」
「何かしらのルールに従わなきゃいけないのでは」
といった漠然とした不安がつきまとっていました。
解消のヒント:「地元の人と話す場」に、思い切って出てみる
わたしの場合、
地域とのつながりを絶やさなかったことが、
安心感につながりました。
私が移住を検討していた下川町では、
当時移住者向けのオンラインイベントが
月に一度開催されていて、
移住希望者も自由に参加できました。
私は継続的にこのイベントに参加し、
町の移住相談窓口の担当者の方と
何度も顔を合わせて話をしました。
こうしたやりとりを通じて、
単なる「一見さん」から
「顔を覚えてもらえる存在」になれたことは、
精神的にも大きかったです。
イベントでは、
実際に移住した方が登壇し、
自分の暮らしについて率直に語ってくれる機会
もありました。
たとえば、
ある移住者の方が話してくれた
「冬の雪かきが不安だったけど、
思ったより公共の雪かきサービスが充実している」
といった実感ベースの話は、
ガイドブックには載っていない
リアルな暮らしの空気を伝えてくれました。
また、
「最初から地元の人と深く関わろうとするより、
まず“無理なく顔見知りを増やす”のがコツ」
といったアドバイスも、
私にとっては実用的でホッとするものでした。
こうしたリアルな声に定期的に触れていたことが、
将来のイメージを具体化する手助けになり、
「この町での暮らしも悪くないかもしれない」
と思えるようになったのだと思います。
不安は、無理に解消するものではなく
少しずつ“馴染んでいく”もの。
そのために、
地域と“継続的に関わる場”を持つことは、
静かに大きな支えになると感じました。
「地域に馴染めるか不安」な人に伝えたいこと
人間関係の不安は、
完全に消えることはないかもしれません。
でも、“いきなり深く馴染む”ことを
目指さなくても大丈夫です。
むしろ、
「まずは自分のペースで接点を持つ」
くらいのスタンスが、
地方で長く心地よく暮らすためには
ちょうどいいのかもしれません。
「地方移住 不安」で検索するあなたにとって、
最初の不安が「完全に解決された」から
移住した人は、ほとんどいません。
みんな、
「ちょっと不安が残るけど、それでもやってみたい」——
そのくらいの感覚で動き始めているのです。
不安があるのは当たり前。
でも、その不安とどう付き合うかで、
未来は確実に変わっていくと思います。
🟪「地方移住 検討中」ならまず見てほしいリアルな情報源とは?
「移住したいけど、まず何を調べたらいいの?」という人へ
移住に興味が出てきたとき、
次に多くの人がつまずくのが「情報収集」です。
ネットで「地方移住」と検索すれば、
自治体のPR記事や理想的な移住生活の写真は
たくさん出てきます。
でも、実際に自分がその土地で働き、
暮らしていく姿をイメージするには、
もう少し「生活者目線のリアル」な
情報が必要になります。
移住相談窓口は、想像以上に“親切な現場”だった
私が最初に相談したのは、
北海道の根室市、新得町、鶴居村などの
役場にある移住相談窓口でした。
地方自治体は今、
移住者を本気で増やしたいと考えているところが多く、
相談窓口の対応も非常に丁寧です。
特に参考になったのは、
公営や民間の住宅供給状況や、
物件の探し方まで教えてもらえたことです。
移住の現実に関わる情報は、
SNSだけではなくこういった
“公式だけど生活者目線に近い窓口”
にあると強く感じました。
オンラインで一気に話を聞くなら、合同相談イベントもおすすめ
私が参加したのは、
北海道内の約20市町村の
移住相談担当者が集まる
オンラインの合同移住相談イベントです。
Zoomのブレイクアウトルーム形式で、
各市町村の担当者と1対1で短時間ずつ
話せるスタイルだったのですが、
話してみたら、なんとなく雰囲気が一番合った
と感じたのが、今住んでいる下川町でした。
担当者とのやりとりを通じて、
その土地の空気感が自分の感覚とフィットしている
ことを直感的に感じました。
(後日お試し滞在をすることになるのですが、
お話する機会を持てた移住経験者の方々には、
不思議と“自分と似た感性の人たちが集まっている”
という印象を受けました。
あの直感は当たっていたのです。)
具体的な情報だけでなく、こうした
「話してみて感じる匂い」や「人の空気感」こそが、
移住先を選ぶ上での大きなヒント
になったように思います。
こうしたイベントは、
時間もお金もかけずに、
複数の自治体のリアルな話を
一気に比較できるのが最大の魅力です。
「誰と話すか」「どんな雰囲気を感じるか」——
そういった小さな感覚を確かめに行くことが、
後悔しない移住の第一歩になるのかもしれません。
実際に相談して見えた“選ぶ基準”
どんな土地が自分に合っているのか?
相談を重ねる中で、
私が自然と大事にしていたのはこんなポイントでした。
- 無理せず住める住居があるか(民間賃貸、公営住宅、空き家バンクの状況)
- 地域の人との距離感(濃すぎないが、孤立しない)
- 町の空気感や景観(言葉にできなくても“なんとなく合う”感覚)
こうした
「行ってみないとわからないこと」
の予測材料としても、
オンライン相談はかなり有効です。
情報収集の正解は、“信頼できる人に会う”こと
検索しても正解が出ないときこそ、
人に会ってみることが一番の近道だったと思います。
その町で働いている人、
住んでいる人の話を聞けば、
自然と「この町で暮らす自分」を
想像できるようになります。
「地方移住 オンライン相談」
「〇〇市 移住 窓口」
などで検索すると、
多くの自治体が定期的に相談会を開催しています。
気軽に話を聞いてみるだけでも、
移住はぐっと現実に近づいてきます。
🟪 働き方を変えたいけど移住はまだ…そんな人が今すぐできること
「地方移住を検討中だけど、今すぐは無理」——
そんな人こそ、 まずは“暮らし”と“働き方”を
少しずつ変えていくための行動を積み重ねてみませんか?
ここでは、私が実際に試してよかったこと、
今だからわかる視点からのおすすめをまとめました。
【地方移住前にできること①】短期滞在で「暮らしに触れる」
- 2〜3日の休みを使って、地方での“暮らしに近い体験”をしてみる
- 宿泊はホテルより、地元のゲストハウスがおすすめ(オーナーと話せる)
- 地元のカフェやイベントに立ち寄って「生活の空気感」を味わう
- 役場の移住窓口にふらっと立ち寄って話を聞いてみる(資料ももらえる)
ポイント:「旅行」ではなく「暮らし体験」の視点で過ごすと、本当に必要な変化が見えてきます。
【地方移住前にできること②】働きながら滞在するなら“準備”がカギ
- Wi-Fi環境は必ず事前に確認(場所によっては弱い)
- 必要な業務時間を先にブロックし、それ以外は自由に動けるようにする
- テザリングなど、通信手段のバックアップを用意しておく
- “自然に触れる時間”を積極的にスケジュールに組み込む
ポイント: 「暮らし」と「仕事」を両立する体験を積むことで、将来の働き方がよりリアルに想像できます。
【地方移住前にできること③】不安があるなら“人と話す”
- 各自治体のオンライン移住相談イベントに参加する
- 担当者と話すことで、支援制度や住宅事情などの具体情報が得られる
- 実際の移住者の話を聞くと、理想と現実のギャップも把握できる
- 「なんとなく合いそう」という感覚も、実は大事な判断材料
ポイント: 移住の意思決定は、情報収集というより“感覚の確認”であることも多いです。
【まとめ】「全部を変える」じゃなくていい
- いきなり引っ越す必要はありません
- 少しずつ暮らしの質を変えていくことが、働き方の再設計につながります
- 「1回やってみる」だけで、大きなヒントが手に入ることも
「移住前にできること」「働き方 小さく変える」などで検索している方へ。
「ちょっと試してみる」——
たったそれだけで、
あなたの働き方や暮らしの可能性が、
静かに動き出すことがあります。
もし、まだ確信が持てなくても大丈夫。
変化は、“始めてから”見えてくるものだから。
まずは、小さく一歩踏み出してみませんか?
暮らしと働き方の再設計は、
もうあなたの中で始まりつつあるのかもしれません。

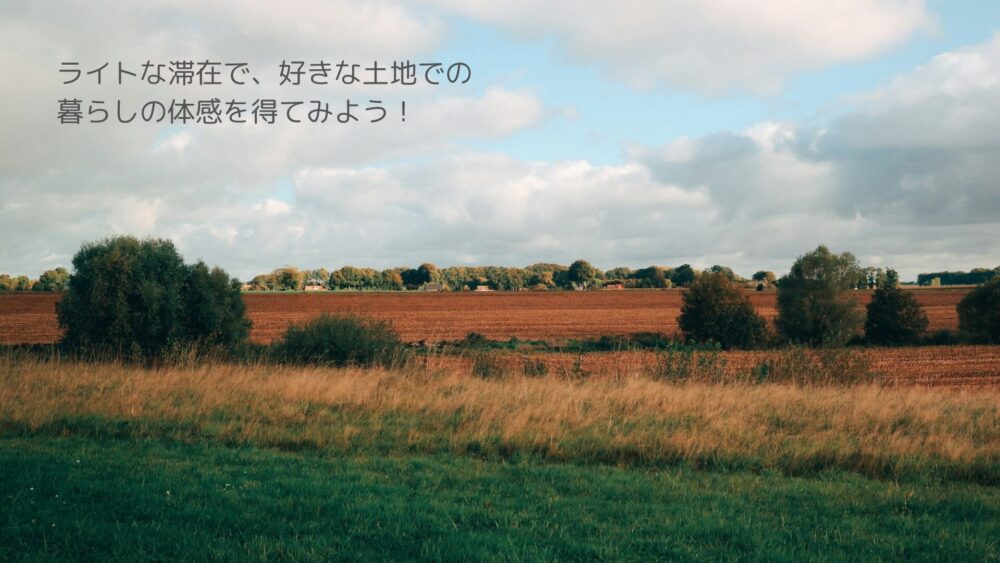

コメント